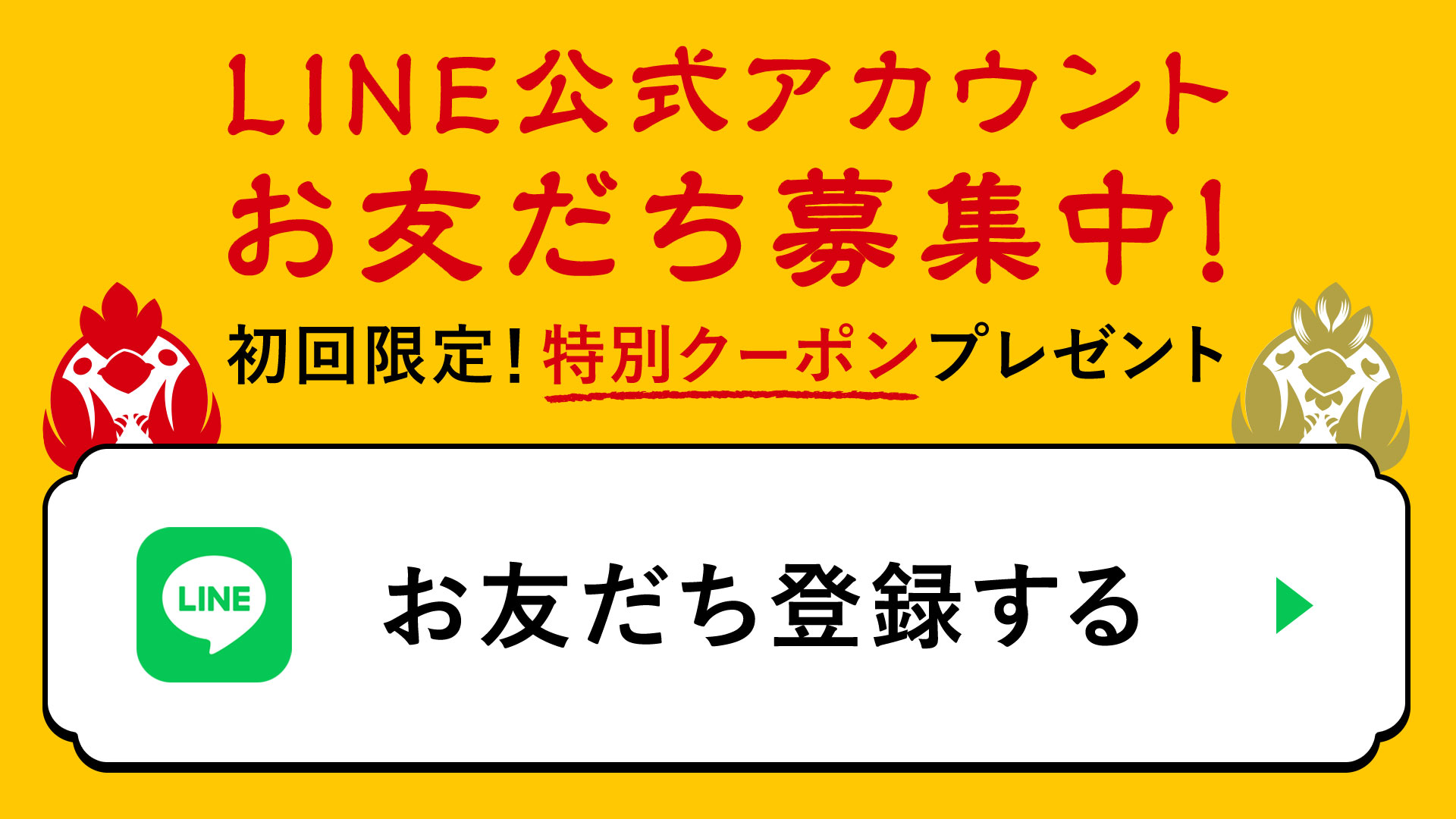ニュース
2020.02.15
ウイスキーの製造過程の蒸留とは?大事な工程だった。

ウイスキーの特徴は度数が高く、少量でも酔いやすいですよね。それは発酵を終えた後、蒸留という過程があるからです。これにより最初は数%程だったアルコール度数を一気に上げることができます。今回はそんなウイスキーの「蒸留」をピックアップしていきたいと思います。
蒸留とは
ウイスキーの蒸留というと、アルコール度数を上げるための作業です。方法は2つあり、「単式蒸留器」と「連続式蒸留機」です。それぞれ使用する機械の形状が異なり、単式蒸留器は「ポットスチル」と呼ばれ、連続式蒸留機の機械は「搭状」です。蒸留は、水とアルコールの沸点の違いを利用した仕組みで、水の沸点が100度に対してアルコールの沸点が80度なので、まずアルコールを先に気化させ、これを冷却、液体化します。この工程のより、アルコールや香気成分といった揮発成分だけを抽出することができるのです。発酵を終えてできたウォッシュ(もろみ)はアルコール濃度が7%程度しかありませんが、蒸留を行うことにより、65%~70%にまでいっきに濃縮されるのです。それでは2つの特徴の違いを見ていきましょう。
単式蒸留
単式蒸留では、銅製の蒸留器のポットスチルを使用します。ポットスチルは手作りです。ですから蒸留所によって形や大きさもいろいろで、ウイスキーの味が決まるといわれています。連続式蒸留器とくらべて手間と時間はかかりますが、よりウイスキーの個性がだしやすい、職人的な蒸留方法といえるでしょう。
単式蒸留器の特徴は、1回ごとにウォッシュ(もろみ)を入れ替えることです。
単式蒸留器での蒸留は通常2回行われ、第1回目の蒸留を初溜、2回目を再溜といいます。
この蒸留方法は蒸留のなかでは最も単純な方法で、主に日本、スコットランドのモルトウイスキーや、アイルランドのシングルポットスチルのウイスキーに使用されています。
連続式蒸留
一方、連続式蒸溜器(パテント・スチル)の特徴は、ウォッシュ(もろみ)を連続投入できることです。ですからアルコール度数を95%近くまで上げられ、短期間に大量の蒸留できます。その名の通り蒸留器の中で、繰り返し蒸留が行われていることから、連続式蒸留と呼ばれています。短時間で、一気にアルコール度数を上げることができるため、原料の風味が残りにくく、クリアな味わいのウイスキーが出来上がります。日本やスコットランドのグレーン・ウイスキーにこの方法が使われています。
鳥メロのウイスキーとオススメ料理
ニッカウヰスキー
ブラックニッカ〈シングル〉399円〈ダブル〉599円〈ボトル〉2000円
スーパーニッカ〈シングル〉599円〈ダブル〉899円
国産鶏もモモたたき 599円
国産鶏のとりわさ 599円
鶏料理が豊富な「鳥メロ」の鶏のお刺身とウイスキーを合わせてみてください。
タグ一覧
月別一覧
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年7月
- 2018年5月